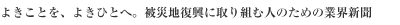役場初の「よそ者」登用で加速した島の観光と商品開発。

本島からフェリーで30分の伊江島。タッチューの名で親しまれる島のシンボル、城山(ぐすくやま)が迎えてくれる。
このような成長の立役者の一人が、島外から役場職員に採用された松本壮(つよし)さんだ。なかなか差別化が難しい沖縄の土産物や観光の競争の中にあって、どのように伊江島を盛り上げていったのか。成功ポイントを聞きに島を訪ねた。

島の景勝地、湧出(わじぃ)展望台からの眺め。波打ち際に真水の湧くポイントがあり、昔から島人の大切な水資源だった。ソーダもラムも、この湧水を利用している。
着任当時、5月に100万輪のテッポウユリが咲く「ゆり祭り」などを中心に、観光集客は年約8万人。しかし島にとって収益の主役はあくまで一次産業で、観光業はプラスαという位置づけだった。松本さんは、過疎高齢化の流れの中で、伸びしろがあるのは観光だと役場内で訴えていった。
年5億円を生む民泊。うるるん体験が人気
伊江島では03年から民泊事業を開始。特に1泊2日で中高生を農家などへ受け入れる、修学旅行の民泊プランに力を入れた。料金は1人9500円で、内7千円が受け入れ先の家に前払いで支払われる形だ。訪れた生徒たちは、受け入れ先の家業を手伝い、夜は星を見ながら「伊江島の両親」と語らい、涙を流して別れる。我が子のように遠慮なく叱り、愛情を込めて子供たちと向き合う島の人々の性質が活き、体験を通じて成長したという声や、受け入れ先を再訪する生徒も出るなどして、急速に人気が広がっていった。
脱ありがちの商品開発。ソーダとラムが誕生

ご当地ソーダ飲料「イエソーダ」。現在ドラゴンフルーツやシークヮーサーなど沖縄の原料にこだわった全4種を展開している。
そして07年に誕生したのが、湧出(わじぃ)と呼ばれる天然の湧水を使用したご当地飲料、「イエソーダ」だ。開発中はなかなか賛同が得られなかったが、発売後年間12万本を売り上げる大ヒットを得て、役場内の空気が変わっていった。松本さんは、開発の最初に「黒糖コーラ」が完成した時、「これで地元産のラムコークが飲みたいな」と思ったという。

島のサトウキビを活用した新商品、「イエラム サンタマリア」。樽で熟成させたゴールドと、ステンレス樽で貯蔵したクリスタルの2種。720ml・2500円、300ml・1400円。
名前に聖母マリアをつけたのは、江戸時代に伊江島のテッポウユリ=琉球ユリが海を渡り、欧米でキリスト教の行事に欠かせないイースターリリーとして定着したことから。「国内に留まらず世界に羽ばたくラムへ」という大きな希望が込められている。
Tweet